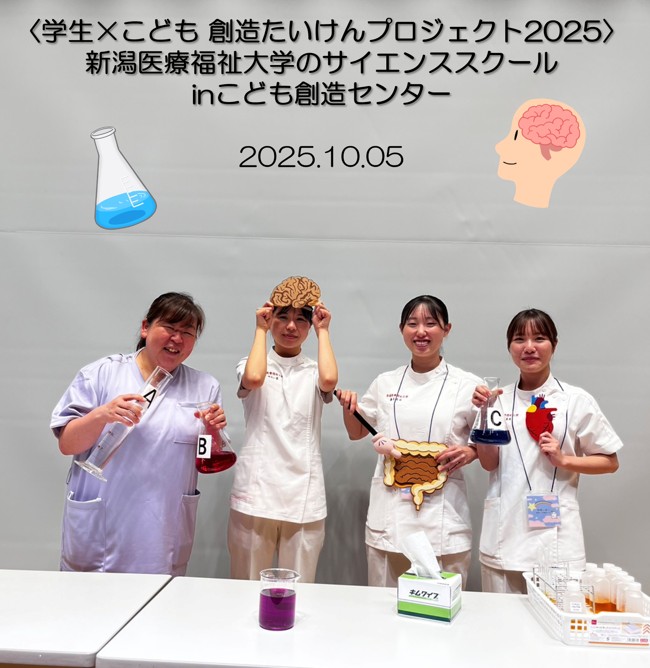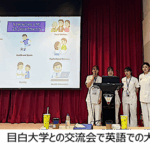2025.11.22
2025.11.22
14日(金)の午前中は、CSMUの大学院生や4年生による研究発表会を聞く機会がありました。発表では、「脊髄小脳変性症3型(マシャド・ジョセフ病)の原因と考えられている活性酸素の抑制方法」や、「寄生虫(Toxocara canis)による肺損傷」、「BRCA1/2遺伝子欠損患者におけるメルファランの効果」など、主に病気の仕組みに関する研究が紹介されました。英語でのプレゼンテーションだったため、スマートフォンの翻訳機能を使いながら理解しようと努めましたが、専門的な内容で難しく感じる部分も多くありました。
その中でも、活性酸素の除去に注目し、ウェスタン・ブロッティング法を用いてタンパク質を分析している研究が多かったことが印象に残りました。
後半は、台湾の教育制度についての発表があり、日本との違いについて考える機会となりました。特に驚いたのは、台湾には国家試験のための予備校があり、今ではほとんどがオンラインで行われているという点です。4年生の初めに入会し、実習と並行して各自で学習を進めているとのことでした。また、台湾の臨床検査技師の国家試験は6科目・各80問(四者択一式)で、各科目に1時間が割り当てられ、年に2回実施されると聞きました。夏の合格率は全国で30%、冬はわずか5%と非常に厳しい試験ですが、CSMUでは合格率が70%を超えるとのことで、大変驚きました。

夜には、台湾料理店で盛大なフェアウェルパーティーが開催されました。最後には先生方や学生の皆さんから、レモンケーキやスナック菓子など、たくさんの台湾のお土産をいただき、とても嬉しかったです。
今回、海外に住む同年代の学生たちと直接関わる機会を通じて、英語でのコミュニケーションの難しさを強く実感しました。相手が英語で話してくれている内容がうまく理解できなかったり、自分が伝えたいことがあっても英語が出てこず、思うように会話ができない場面が何度もありました。台湾の学生は、小学校から英語教育を受けていると話していましたが、それは日本でも同様です。それにもかかわらず、彼らの英語力の高さに驚き、英語教育の方法に大きな違いがあるのではないかと感じました。また、スマートフォンの翻訳機能を使って意思疎通を図ろうとする場面もありましたが、翻訳された日本語が不自然で意味が通じにくかったり、こちらの意図が正確に伝わらないことも多く、翻訳機能の限界を感じました。このような経験を通して、次に外国の方と交流する機会までに、もっと英語をしっかりと身につけたいと強く思いました。今後は積極的に英語学習に取り組み、実際の会話に活かせる力をつけていきたいです。
成田空港に到着し、入国審査を通過して出口を出たときには、皆で無事に研修を終え、日本に帰ってこられたことへの安心感とともに、楽しかった日々が終わってしまうことへの少しの寂しさも感じました。この研修を通して、他のメンバーの新たな一面を知ることができ、6人の仲がより一層深まったと感じました。
10日間という限られた時間の中で、たくさんの貴重な経験をすることができ、本当に楽しく、充実した研修となりました。一生の思い出になるような素晴らしい時間を過ごせたことに、心から感謝しています。
⇧⇧⇧
参加学生の言葉をかりて発信していますが、
このように、非常に有意義かつ、日本では経験できないような貴重な経験だったのではないでしょうか?
一歩踏み出すことで見える世界があることを強く感じます!🌎
英語に関しても、言語の違いだけでなく、文化背景の違いが相まって、コミュニケーションの難しさを実感することがあります。
違いや至らなさを感じるだけでも意味があるのかなと個人的には思います。
ぜひ、臨床技術学科に来ていただいたら、一緒に未知の世界に行ってみましょう!🚀
全力でサポートします!😍😍